横山 彰人 著
第6章 子どものために
子供に恵まれたのは、結婚して二年目の春だった。二人とも春の季節が好きだったので、出産五ヶ月前には、男の子なら春のやわらかな陽にちなみ「光」、女の子なら「陽子」と早々と決めていた。
「どんな子ができるんやろな。きっと男の子なら、武ちゃんに似て男前でやさしい子やと思うわ」
「こんなギスギスした世の中に生まれてくる子供も迷惑な話だと思うけど、男の子ならたくましく育って欲しい。もし女の子なら咲子のように愛らしく、やさしくて料理の上手な子に育つといいね」
「私は男の子でも女の子でもどちらでもいいけど、私ら以上に大きな人間になって欲しいわ。その為の勉強は0才教育からって言うやないの」
子供の出産を待ちわびつつ、夫に打明けることのできなかった社宅での悩みを、子供が生まれる機会に引越をし、解消したかった。そして、新しい家は新築分譲マンションと決めていた。
日曜日、夫が何気なく新聞のチラシを見ている時、咲子は思い切って
「武ちゃん、子供が生まれたら、どっかええマンションあったら引越せへんか」 と聞いてみた。
「引越すってどこに? この社宅は住み心地はいいし静かだし、会社にも近いし子育ての環境にしてもいいじゃないか。咲子だって気に入ってるんだろ。
子供が生まれるか生まれないかで引越すのは大変だし、家選びも大変な労力がいるぞ。そんな時間もないし」
武夫の考えは分っていた。この社宅は回りの住環境を含め気に入っていたので、ここで子供が小学校にあがる頃まで住み、それまでに住宅購入資金を少しでも蓄えておきたいという気持ちなのだ。
しかし咲子にとって、どうしてもこの社宅を引越したい理由がほかにもあった。それは、生まれてくる子供にいい家の記憶を残してやりたかった。
母親が社宅ゆえの人間関係にイライラし、ストレスをためながら過す家は、子供にとっても良くないと思った。母親の精神状態は、無意識であっても子供に伝わることは、半年前に読んだ精神医学の育児書にも書いてあり、そんな状況での子育ては避けたかった。
そしてもうひとつこれも武夫には言えないが、咲子の育った家は商家とはいいながら木造二階建てで、事務作業所のほか、離れの納戸や屋根裏部屋も含めると、一般住宅よりはるかに大きい家だった。正直言って社宅の3DKよりもっと広い家で、できることならのびのびと子育てをしたい。
武夫と二人の生活は住み心地は良くても、子供を育てる住まいという事になると別だと考えていた。エリート教育をする為にも住環境を変えたかったし、それが子供の幸せにつながると強く思っていた。
「でもね武ちゃん、いずれこの社宅から出んならんことが決まっている以上、いいところがあったら早く移った方が、子供のためにもいいんとちがう。幼稚園に入ってからとか小学校に入ってから引越すと友達がいなくなったり、一貫した私立の教育を学ばせる面からも、マイナスの方が多いと思うわ」
「その考えに僕も賛成しないでもないけど、しかし購入資金の頭金も無いから全額ローンを無理して組んでも、今の収入では小さいマンションか通勤時間二時間以上の遠いマンションしか買えないぜ」
「遠いところはイヤ、生活に不便だし、いい幼稚園もない」
「ねえ武ちゃん生まれてくる子供のためにここは京都のお父ちゃんに相談してもいい」と咲子はそこまで言うと武夫を見た。
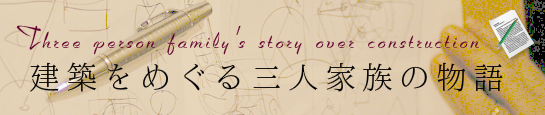
 第5章 社宅の不満
第5章 社宅の不満