横山 彰人 著
第23章 幻想
咲子は会話が途切れたまま、ぼんやり窓を見つめていた。雨はいつの間にか止んでいた。窓ガラスは雨で埃が流れ落ちたのか、遠く暗闇の中にいつもより多くの街の灯が見えた。遠く三浦半島の方に目を移すと、月が出ているのか、暗い海の中で波が光っていた。街の灯ひとつひとつには灯の数だけ家庭があって、その数の分だけ温かな幸せな家族があると思った。そんな事はあり得ない話だと思うが、今の咲子にはそう思えた。
和室で寝ている光は、先ほどまで壁側を向いていたが、いつの間にか寝返りをうって、安らかな寝顔を見せていた。
また涙が溢れてきた。咲子は、光をもとの元気な明るい光にしなければ絶対にいけないし、夫と別れても何の解決にならないどころか、もっともっと光を苦しめることになるのではないかと思った。誰もが羨ましがられるマンションに移って、たった六ヶ月でこんな状況に陥ってしまったことが信じられなく、そして悲しかった。
武夫は黙って椅子から立ち上がり、「俺は疲れた。明日早いから」
と一言言うと、そのまま寝室には行かず、隣の和室に寝ている光のそばに行き、しばらく顔を見つめ寝室に行ってしまった。
咲子はもっと話をしなければならないことが沢山あるのは分っていたが、呼び止めて話を続ける気力もなくなっていた。
二人の心の溝が段々深くなっていって、やがて努力しても埋め切れなくなるような予感がして、思わず心が震えた。
幸せになろうと思い、武夫と結婚し、光を生み、さらに大きな幸せをつかむため家を購入したのだ。
今その幸せが、音をたてて崩れていくような気がした。
窓を開けると、湿気を含んだ冷たい風が頬をなで潮の匂いがした。ちょうど去年の今頃は一生懸命マンションを探して、いろんな資料や販売図面を見て必死だったことを、遠い昔のように思い出していた。渋谷の社宅からこのマンションへ移って、何を得て、何を失ったのだろうか。
咲子は、いつまでも暗い海の先の遠くの灯を見続けていた。
武夫は、寝室に戻ってから、なかなか寝付かれなかった。頭の一点がしこりのように固くなって、何かを考えようとしても容易に焦点が定まらなかった。窓から見える夜空には、いつもより多い星が瞬いていた。雨上がりで空気が澄んでいるせいか、こんなに沢山の美しい星を見たのはいつだったろうか。
じっと記憶の底をたどっていくと、なぜか生まれ育った長野で過した冬の星座に行きついた。シーンと静まり返った白い雪の世界。確か六歳か七歳の頃無数の星と雪明りの中、家の縁側に天体望遠鏡を持ち出して、父ときらめく星座を見た記憶。母と雪道を手と手を繋いで歩いていて、滑って転んだ時見上げた星と雪の匂い。思い出せばそれぞれの季節には、強烈にその季節の匂いと色があった。春は若葉のむせ返る緑の匂い。秋は枯葉の乾いた匂いと空の色。
夜はいつも家族が揃い、父の膝の上に抱かれて食事をしながら、いつの間にか寝てしまい、目が覚めると布団の中に母の温もりがあった。家族の情愛に包まれて育った遠い日の記憶は、振り返れば壁に突き当たった時、どれだけ乗り越える力を与えてくれたか、武夫は思った。
そんな記憶を辿っているうち、先ほどまで言い争い、感情的になった気持ちが、自然に穏やかな気持ちになっていった。同時に、光に親として自分が経験したと同じような豊かで温かい、いい記憶を残してやれるだろうか。また、縁側や茶の間で楽しく家族と過したような、いい家の記憶を残してやれるだろうかと考えると慄然とした。
現に光は〝無気力症候群〟と診断され、親として子育て失格の烙印を押されているのだ。その現実に、咲子は打ちのめされ、その責任を身ひとつで受けとめようとしている。一人の努力ではどうにもならないところに来ているんだろうということだけは、容易に想像できた。
学生時代、東京で過していた頃、中学生や高校生による様々な犯罪や事件、そして学級崩壊が報道され、その遠因が乳幼児や幼年時代における家庭環境にあることが、大きく影響していることが社会問題になっていた。そんな報道を見るにつけ、武夫は漠然と子育ては長野でやりたいと思っていた。豊かな自然、明るくのびのびと育った自分の幼年時代と重ね合わせていた。しかし、そのためには、就職は地元に帰らなければ成り立つ訳はなく、東京で就職を決めた時その事は忘れた。
不思議なことに咲子と結婚し、光が生まれた時も自分が咲子とどんな子育てをしようかということや、どんな人間に育てたいかという思いは全く抜けていた。同時に東京の子育ての環境がどんな状況にあるのかも、知ろうとしなかった。
会社は忙しく、ようやく会社の中で自分の力を発揮でき、次の昇進のステップが見えてきた時期で気がつくと、全て咲子に子育ても家の問題もまかせてしまっていた。
つい数時間前まで、家族の幸せは会社で地位を築き、給料も上っていくことによってもたらされるものと信じていた。会社での競争に敗れることイコール家庭崩壊と思い、必死で頑張ってきた。しかし今、人ごとだと思っていた「父親不在」の結果として、息子の「無気力症候群」という病気を突きつけられ、受け入れることしか出来ない現実にたじろいだ。
自分が信じ描いていた、幸せな「家族という物語」が、咲子の思う家族の幸せのあり方と、大きく異なっていたのだ。会社の出世、その結果としての恵まれた給料が、幸せな家庭をつくるということが幻想であり、そのことが咲子に重荷を負わせ、傷つける結果になってしまったのかもしれないと思った。
光が成長した時、親として胸を張って光の目を見ることができるだろうか。このままだと、誰よりも自分自身が、一生悔やんでしまうのではないか。
今本当に必要なのは、咲子と一緒に悩み、時には譲ることを積み重ねながら、二人で試行錯誤していくことではないのか。
会社人間で子育てに無関心、父親不在、そして致命的な妻とのコミュニケーション不足による夫婦の危機を、光の病気が気付かせてくれたと思った。
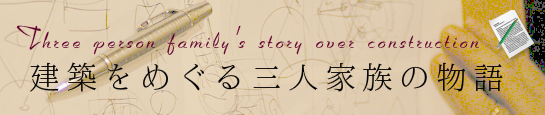
 第22章 原因
第22章 原因