横山 彰人 著
第3章 記憶の原風景
武夫と咲子が始めて出会ったのは、武夫が就職して四年目に咲子が新入社員として同じ総務課に配属され、近くのイタリアンレストランでの歓迎会の時だった。
咲子は部長からあいさつを促され緊張した顔で、「上田咲子と申します。京都で生まれ育ちました。京都しか知らへん女どす。東京の会社に就職するのは両親は反対どしたけど、なんか東京の空気を吸って一回りも二回りも自分を大きゅうしたいと思いました。よろしくお願い申します」関西弁というか京都言葉と標準語が混じった変なイントネーションの言葉だったが、咲子の誠実さも出ていて武夫は好感を持った。また咲子が京都育ちということも興味をそそられた。
武夫は学生時代から京都が大好きで、日本歴史研究会の同好会に所属していたこともあって、京都、奈良には幾度か訪れていた。先輩に京都は四季を通じて行かないと、ほんとうの良さは分からないと言われ、長野の実家へ帰省する時や東京に戻る時もわざわざ富山や福井を経由し京都に寄ったものだった。
就職してからは仕事が忙しく、京都から足が遠のいてしまったが、久し振りの京都言葉や母親に横顔が似ているような、自分好みの顔立ちに引かれ、話をしてみたいと思った。
立食形式の歓迎会で、咲子は武夫と五メートルほど離れ、いろんな人に囲まれ楽しそうに話していた。お酒は見ていた限りではワイン三、四杯ほど飲んでいるから、かなりいける口かもしれないと想像を巡らしていたら、話していた先輩女性に携帯電話が入ったらしく、慌てて出ていった。
武夫はワインを持って近づき、「お代わりいかがですか、入社おめでとうございます。がんばって下さいね」と、とりあえず先輩らしく社交辞令をいい、咲子の反応を伺った。「ありがとうございます。私からご挨拶せんならんのに、堪忍です」
相変わらずゴチャ混ぜの言葉を使っていたが、そばで見ると愛らしく新入社員に一目ボレのような気持ちを抱く、自分自身が信じられなかった。
「私は武井武夫と申します。あなたより四年先輩ということになりますが、分からないところがあれば何でも聞いて下さい。すぐ慣れますからね」会の始めの自己紹介の時は、回りがうるさくあまり印象に残らなかったが、自分に対する細やかな配慮や温厚そうな人柄に、咲子もなぜか分からないが体の何かが動いた気がした。
振り返ってみると、時間にすればわずか五分ほどだったと思うが、武夫は京都が大好きで学生時代から幾度となく訪れたこと。好きな季節は春で、桜の時節になると観光客に人気がある醍醐寺の桜や平安神宮の紅枝垂桜より、たとえば鴨川沿いに下鴨神社から上鴨神社へ続く桜並木の風景の方が好きなこと。対岸の小道から見る鴨川、桜並木、比叡山、そして絹を引くような四月の青い空、そんな情景に心引かれることを一方的に話をしてくれた。
しかし、咲子が「えっ」という声には出さないが、武夫の顔を改めて見直したのは、次の話だった。
「僕が一番好きなのは、京都の夕陽なんです。清水寺の裏手の方から山へ登って、東山の尾根づたいにある将軍塚の展望台から見る夕陽、薄墨色に暮れなずむ京都の街の素晴らしさ。そこは僕が京都に行くたびに夕方近くになると必ず足を運ぶところでもあるんだ」将軍塚は椎武天皇が平安京の造営時、都を鎮める意味で将軍像を埋めたと言われている所で、京都市街が一望でき京都を舞台にしたテレビのサスペンスドラマにもよく使われている場所でもあった。
東山高校と位置的にはほぼ同じで、大好きな西山に沈む夕陽が武夫も好きだという偶然性に驚いた。
そして、初対面とは思えない同質な心の原風景みたいなものを感じて熱くなった。
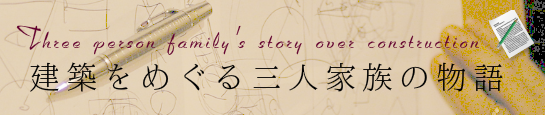
 第2章 町屋の家
第2章 町屋の家